 |
名古屋鉄道2000系(その1) |






|
コンテンツ掲載日:2005年03月20日
最終更新日:2007年02月20日 |
|
その1>>|その2|その3|その4|その5
|
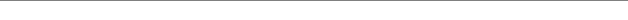
|
|
◆車輌概説
名鉄2000系は、2005年1月に開港した中部国際空港へのアクセス用特急車両として2004年5月に誕生しました。既にその5年前に登場している1600系に近いコンセプトを持ちつつ、空気バネの力で車体を傾斜させることによって曲線区間を高速で走行できる技術が本格採用されたほか、車体には空と海の青、白い雲を基調としたカラーリングが施されるなどしています。このように同系は赤色がベースカラーとなって幾久しい名鉄車両の中にあっては非常に特異な存在であり、「空港へ行く特急」としての十分なインパクトを持った車両となっています。空港開港を目前に、公募によって『ミュースカイ』という愛称が与えられた同系は、3輌1編成の組成で合計10編成が用意され、2005年1月より名鉄の新しい看板車両としての活躍を始めています。
|
|

写真ご提供:佐藤A哲也様
|
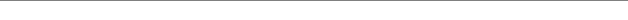
|
|
◆さあ、どうしましょう?
JR東日本のE257系特急電車を思わせる独特な車体断面形状を模型で再現することについては、過去に同じ形状を持つ名鉄1600系を製作した経験もあるので不安はありませんでした。一方、ポリカーボネイトと呼ばれる樹脂で覆われたブラックマスクをどのように表現してよいものかということについてはずいぶん悩みました。
結局、悩み続けても何ら進歩がないということになりましたので、「とりあえず形だけは作ってしまおう。」ということになりました。まずは、いつものように製作用の図面作りから着手することにしました。今回は、わが国三大模型誌の一つである『月刊とれいん』に同系の詳細な図面がこれまた詳細な紹介記事とともに掲載されていますので、これと実物誌『鉄道ファン』を参考にしました。
|
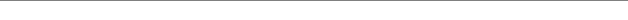
|
|
◆車体の切り抜きと組立て
同系の車体断面は、屋根が一段落ちたような構成になり、かつ車体の裾が窓の下から内側に向かって緩やかにすぼまり、床下近くでこれが終わって垂直方向に変化するといった具合になっていますから、側板と屋根板を初めから一体になった材料で構成することは困難です。車体の構成は、内張りも含めて【図1】の示すとおりとなっています。すなわち同系の車体は、これに両妻板を含めた六面体を作るような要領で形作ることになります。
|
|
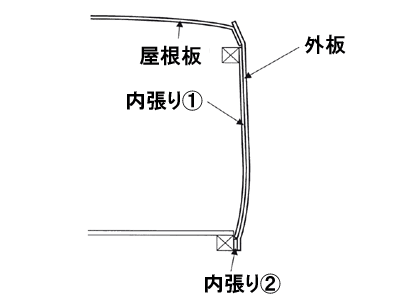
【図1】
|
|
図面から材料へのケガキ入れが完了したら、材料を切り出しました。その際、裾の部分の曲げグセを付けやすいように、多少の余白を残して切り出しておきました。続いて【図2】の示すように屋根の方のカーブが始まるところと床板近くで裾の絞りが終わるところの両方に、カッターナイフでスジを入れておきました。そして、【図3】の示すようにまずは裾の部分について曲げグセをつけた後、裾の部分を本来の寸法でカットしました。
|
|
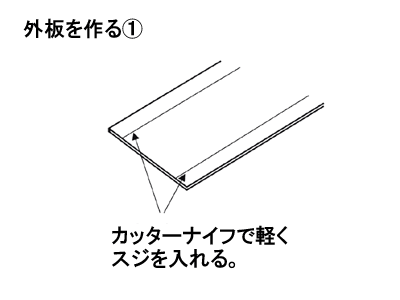
【図2】
|
|
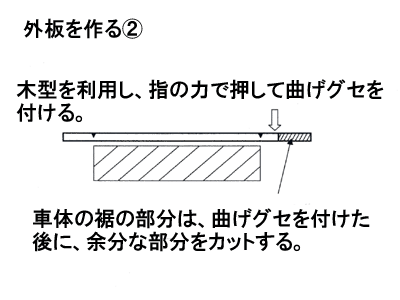
【図3】
|
|
続いてその材料の表裏をひっくり返して、【図4】の示すように木型にあてがって指の腹でしごくようにして屋根の肩と窓下に曲げグセを付けておきました。窓抜きと内張りの接着に取り掛かるのはこれらの作業が済んでからです。内張りの接着が終わったら、再び曲げグセをつけてやり、車体が元の形状に戻らないように気をつけました。
なお、妻板については特別な工夫を行うことなく、ごく普通に作っています。
|
|
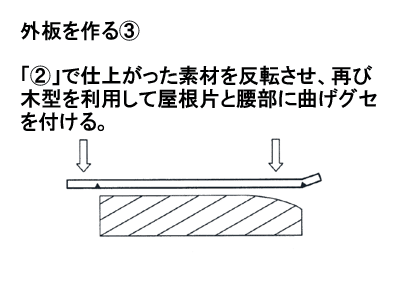
【図4】
このページのトップへ
|
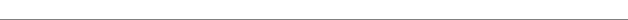
|
|
その1>>|その2|その3|その4|その5
|